動産物権変動における公示と公信(2)
公示の原則と公信の原則との関係
(1)不動産物権変動と動産物権変動との比較
公示の原則と公信の原則との関係を整理しておこう。
①Aは、Bから、Bが 所有する物を買い受けた。 その後、 Bは、 Cに対しても、その物を売却した。
②Aは、Bに対し、 自分が所有する物を賃貸して、これを引き渡した。
その後、Bは、その物が自分の物であるとして、そのことを過失なく信じているCにその物を売却した。
① は、 二重売買型の例であり、②は、他人物売買型の例である。
まず、目的物が不動産であるときについて、 検討をおこなう。
①では、BからAへの所有権移転登記がされたときは、 Aは、Bから所有権を取得したことを第三者であるCに対抗することができる (177条)。
この場合において、C は、Bから善意無過失でその不動産を買い受けたとしても、 94条2項類推適用による保護を受けることができない。 登記名義は、BからAへと移されているからである。
これに対し、②では、Cは、原則として、所有権を取得することができない。もっとも、登記名義がAからBへと移されていたときは、Cは、 94条2項類推適用によって保護される余地がある。
このように、 不動産物権変動では、AとCとの関係は、①については、 177条の規定によって定まり、②については、 94条2項類推適用によって定まる。
では、 目的物が動産であるときはどうか。
②では、Cは、原則として、所有権を取得することができない。 この場合において、Cが所有権を取得することができるかどうかは、 192条の規定によって定まる。 そして、このことは、①において、BからAへと占有改定による引渡しがされたときであっても、同じである。
たしかに、この場合には、Aは、Bから所有権を取得したことを第三者であるCに対抗することができる (178条)。
しかし、Cは、 動産を占有するBがその所有者であると過失なく信じてBからその動産を買い受け、その占有を始めたときは、 192条の規定による保護を受けることができる。
このように、動産物権変動では、AとCとの関係は、②については、 192条の規定によって定まり、 ①についても、占有改定による引渡しがされたときは、最終的には、192条の規定によって定まる。この意味において、 178条の規定の存在意義は、乏しいものとされている。
(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第178条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
(即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(民法・e-Gov法令検索)
(参考)物権法[第3版] NBS (日評ベーシック・シリーズ) 日本評論社


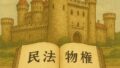

コメント