「占有を始めた」の意義(1)
(即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(民法・e-Gov法令検索)
(1)占有改定
「占有を始めた」とは、引渡しを受けることをいう。 では、占有改定による引渡しも、「占有を始めた」 に当たるか。
たとえば、次のケースにおいて、即時取得が成立するかどうかが問題となる。
①Aは、Bに対し、自分が所有する工作機械 (甲) を賃貸して、これを引き渡した。
Bは、甲が自分の物であるとして、そのことを過失なく信じているCに甲を売却した。 Cは、Bに対し、そのまま甲の保管を委ねている。
②Aは、Bから、Bが所有する工作機械(甲)を買い受ける一方で、Bに対し、 そのまま甲を賃貸することとした。Bは、甲が自分の物であるとして、そのことを過失なく信じているCに甲を売却した。 Cは、Bに対し、 そのまま甲の保管を委ねている。
(①) は、他人物売買型の例であり、(②)は、 二重売買型の例である。
(a) 肯定説・否定説・折衷説
一般的な見解は、占有改定による即時取得が認められるかどうかについて、他人物売買型 (①) と二重売買型 (②)と区別していない。 一般的な見解は、肯定説、否定説、 折衷説の3説に分かれる。
肯定説によれば、 占有改定による即時取得も認められる。 Cが取得した占有の効力から、Bの占有に対するCの信頼の保護へ、という制度の理解の変遷を推し進めれば、Cが現実の占有を取得したことまでは求められないこととなろう。
これに対し、否定説によれば、 占有改定による即時取得は、認められない。 判例は、この考え方にたっている (最判昭和35.2.11民集14巻2号168頁 〔(①)の類 型に属する事案〕、 最判昭和32.12.27民集11巻14号2485頁 〔(②)の類型に属する事案])。
その理由は、即時取得が成立するためには、「一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得すること」(前掲最判昭和35.2.11)が必要であることに求められている。
学説においても、否定説が有力である。 一方で、Cは、Bから占有改定による引渡しを受けただけでは、保護に値する支配を獲得したとはいえない。Bが甲をなお現実に占有している以上、 Cは、Bがふたたび無権限処分をすることを妨げることができる支配の状態を確立するに至っていないからである。他方で、甲は、Aが現実の占有を委ねたBのところにとどまっている。
つまり、 A の信頼は、形のうえでは裏切られていない (この表現は、 ゲルマン法的思考のなごりである) それにもかかわらず、 即時取得の成立を認めると、A にとって、即時取得の成立を防止したり、 その成否を確知したりするためのモニタリングコストが過大になる。
したがって、 占有改定による即時取得は、 否定されるべきである。
折衷説は、次の考え方をとるものである。 すなわち、 即時取得は、占有改定による引渡しによっても成立する。
もっとも、 占有改定による引渡しがされた時点では、その取得の効果は、 不確定である。 その後、 現実の引渡しがされたときに、その時点で取得の効果が確定する。 否定説によれば、Cは、 現実の引渡しを受ける時点で善意無過失でなければならないのに対し、折衷説によれば、Cは、占有改定による引渡しがされた時点で善意無過失であれば、現実の引渡しがされた時点では善意無過失でなくてもよい。 また、現実の占有がBにある時点で争いが生じたときは、否定説によれば、 Aが優先することになるのに対し、折衷説によれば、 AとCとは、 どちらも相手方に優先することができない(両すくみ) こととなる。
(b)類型論
学説のなかには、他人物売買型(①)と二重売買型(②)とでは、問題の構造が異なるとするものがある。① では、甲の所有者は、Aであった。この場合において、BがCに対し、 甲を無権限で処分している。 そのため、Cは、Aに 劣後するのが原則である。 これに対し、 ② では、甲の所有者は、Bであった。 AとCとは、いずれもBから甲を買い受けた者同士である。 そこで、この場合には、AとCとは、対等な競争者の関係にあるものとみることができる。 ②について、最終的に192条の規定によって処理がされるのは、 178条の「引渡し」 に占有改定による引渡しが含まれるからである。もっとも、そのことは、②を①と同じように処理することを正当化するものではない。
そこで、①については、 否定説をとるべきであるものの、②については、折衷説をとるべきであるとされる。 折衷説は、次の点において、 対等な競争者の関係を定めるのに相応しいルールを示しているものと考えられるからである。 すなわち、 現実の占有がBにある時点で争いが生じたときは、AとCとは、 両すくみとなること、この場合には、AとCとの間の優劣は、現実の引渡しの先後によって定まること、現実の引渡しを受ける時点において、Cは、Aの所有権の取得について悪意であってもよいことである。
(参考)物権法[第3版] NBS (日評ベーシック・シリーズ) 日本評論社



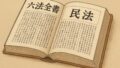
コメント