盗品または遺失物に関する例外(1)
(1)階層的なルール
即時取得に関するルールは、 階層的である。 すなわち、 192条の規定は、無権利の法理の例外を定めるものである。 そして、 192条の規定にも、 例外のルールが定められている。 その例外のルールにも、さらに例外のルールが定められている。
まず、被害者または遺失者は、 盗難時または遺失時から2年間、盗品または 遺失物の回復を求めることができる (193条)。 占有離脱物について は、外観の作出または存続について真の権利者の意思的関与がない。盗取され たり、遺失したりしたときは、意思的関与と同視することができるほどの重い帰責性も、認められないことが多いであろう。そうであるとすると、盗品または遺失物については、原則として、即時取得を認めないとすることも考えられる。 しかし、 日本法は、 被害者または遺失者に対し、 2年間の回復請求を認めるにとどめている。これは、被害者または遺失者の救済を一定期間に 限定している点で、動産取引の安全を促進したものであると評価することができる。
(盗品又は遺失物の回復)
第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
(民法・e-Gov法令検索)
次に、被害者または遺失者は、次に掲げるときは、占有者が支払った「代価を弁償」しなければ、 盗品または遺失物を回復することができない(194条)。
すなわち、占有者が競売もしくは公の市場を通して、 または同種の物を販売する商人から、善意で盗品または遺失物を買い受けたときである。この場合には、動産取引の安全を確保する必要性がいっそう高いからである。
もっとも、 占有者が古物商または質屋であるときは、盗難時または遺失時から1年間は、 盗品または遺失物を無償で回復することができる(古物営業法20条、 質屋営業法22条)。
これらの者は、専門家である以上、盗品または遺失物に当たらないかどうかを慎重に調査すべきだからである。
(盗品及び遺失物の回復)
第20条 古物商が買い受け、又は交換した古物(指図証券、記名式所持人払証券(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百二十条の十三に規定する記名式所持人払証券をいう。)及び無記名証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
(古物営業法・e-Gov法令検索)
(盗品及び遺失物の回復)
第22条 質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。
(質屋営業法・e-Gov法令検索)
(参考)物権法[第3版] NBS (日評ベーシック・シリーズ) 日本評論社


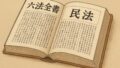
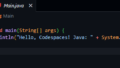
コメント