婚約は、将来の婚姻を約束する合意のことであり、婚姻という本契約に対する予約と捉えられている。
明治民法施行直後の判例は、婚約を無効としたが、婚姻予約有効判決以降は、判例・学説において、その有効性が承認されている。(大審院大正4年1月26日判決 民録21輯49頁)
婚約の有効性を承認する意義は、婚約の不当破棄があった場合に、一方から他方への損害賠償請求を認めることにある。(婚約予約理論)
婚約は当事者間の合意のみによって成立する。
所謂婚姻の予約なるものは結納の取交せ其の他慣習上の儀式を挙げ因て以て男女間に将来婚姻を為さんことを約したる場合に限定せらるべきものに非ずして男女が誠心誠意を以て将来に夫婦たるべき予期の下に此の契約を為し全然此の契約なき自由なる男女と一種の身分上の差異を生ずるに至りたるときは尚婚姻の予約ありと為すに妨げなきものとす。
(大判昭和6年2月20日新聞3240号4頁)
当事者が誠心誠意、将来夫婦になることを合意していればよく、結納の取り交せなどの慣習上の儀式をする必要はないということである。
判例には、外形的な事実が存在しない事案において、将来の結婚を約束して肉体関係を継続していた男女間に婚約の成立を認めたものがある。
婚姻予約の不当破棄による慰藉料の請求が認められた事例。
当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し長期にわたり肉体関係を継続するなど原審判決認定の事情(原審判決理由参照)のもとにおいて、一方の当事者が正当の理由がなくこれを破棄したときは、たとえ当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従つて結納をかわし、もしくは同棲していなくても、相手方は、慰藉料の請求をすることができる。
(最判昭和38年9月5日民集 第17巻8号942頁)
配偶者のある者が他の異性とする婚約については、善良の風俗に反する事項を目的とするものであって無効とする戦前の判例があるが、現在では、婚姻が破綻して事実上の離婚状態にある場合は有効に解してよいとの見解が多数を占めている。
(参考)家族法[第4版]NBS (日評ベーシック・シリーズ)日本評論社



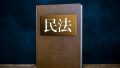
コメント