III 明認方法とは
1 物権変動の対抗要件と物の独立化の要件
明認方法の意義については、次の2つの見解がある。
第1の見解によれば、 明認方法は、もっぱら立木の物権変動の対抗要件の役割を果たすものである。 すなわち、 土地に生立する立木が売却されたときは、 その立木は、明認方法が施される前に独立の物となり、売主から買主への立木所有権の移転の効力が生ずる。 明認方法は、この物権変動を第三者に対抗するための要件に位置づけられる。
これに対し、 第2の見解によれば、 明認方法は、 立木の物権変動の対抗要件にとどまらない。 立木は、原則として、 土地の一部を構成する。 明認方法は、 その例外として、立木を独立の物とするための要件である。 したがって、立木について明認方法が施されたときに初めて、その立木について物権変動が生ずることとなる。
以上の議論を踏まえつつ、明認方法による公示に関するルールについて、あらためて検討をおこなう。
2 立木所有権の譲渡と留保
(1)立木所有権の譲渡
Aが所有する甲土地の上に生立する乙立木について、AからBへと売却がされた後、AからCへと売却がされた。 この場合には、BとCとの間の優劣は、 乙立木についての明認方法の先後によって定まる。 この結論は、第1の見解をとっても、第2の見解をとっても変わらない。もっとも、その説明の仕方が異なる。
第1の見解によれば、BとCは、乙立木について明認方法を施す前に、それぞれ乙立木の所有権を取得する。 そして、 明認方法を先に施したほうが、その所有権の取得について対抗要件を備えることとなる。 他方、 第2の見解によれば、乙立木について明認方法が施される前は、 乙立木は、甲土地の一部を構成 する。したがって、この段階では、BとCは、どちらも乙立木の所有権を取得することができない。 そして、 明認方法を先に施したほうが、 乙立木の所有権を取得するとともに、 その対抗要件を備えることとなる。
(2) 立木所有権の留保
Aが所有する甲土地とその上に生立する乙立木とのうち、 甲土地のみがAからBへと売却され、 乙立木の所有権は、Aに留保された。 その後、BからCへと甲土地および乙立木が売却された。
この場合には、Aは、乙立木について明認方法を施さなければ、乙立木の所有権の留保を第三者であるCに対抗することができない。
第1の見解によれば、この結論は、 「留保もまた物権変動の一場合」であること (最判昭和34・8・7)つまり、 乙立木について、 A→B→Aという物権変動が生じたことから導かれる。
しかし、 Aは、乙立木の所有権を留保している以上、その所有権は、Aのもとから動いていないはずであると批判されている。これに対し、第2の見解によれば、留保について明認方法が求められるのは、当然のことである。 AがBに対し、乙立木の所有権を留保して甲土地のみを売却したとしても、乙立木について明認方法を施す前は、乙立木は、甲土地の一部を構成するものとして、その所有権がAからBへと移転する。
この段階では、Bは、 Aに対し、 留保の合意に反してはならない債務を負担するにすぎない。
Aは、乙立木について明認方法を施したときに、 乙立木の所有権を Bから復帰的に取得するとともに、その対抗要件を備えることとなる。
(参考)物権法[第3版] NBS (日評ベーシック・シリーズ) 日本評論社



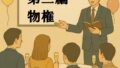
コメント