盗品または遺失物に関する例外(2)
(2)所有権の帰属と使用利益の返還
Aは、自分が所有する照明器具 (甲) を何者かに盗まれた。 その後、甲は、 照明器具の販売業を営むBの手に渡った。 Bは、甲が自分の物であるとして、 そのことを過失なく信じているCに甲を売却した。 Cは、Bに対し、 代金500万円を支払った。Aが甲を盗取された時から1年半が経過した後、 Aは、Cに対し、甲の返還を求めて訴えを提起した。
(a) 所有権の帰属
この場合において、 まず、 甲の所有権は、AとCとのどちらにあるのか。 甲が回復されるまでの間、所有権は、原所有者に帰属するのか、それとも、 占有者に帰属するのかが問題となる。
判例によれば、甲が回復される前にも、甲の所有権は、Aに帰属する(大判大正10.7.8 民録27輯1373頁)。 これは、 原所有者帰属説とよばれる見解である。この見解によると、原所有者の回復請求権は、物の占有の回復を求めるものである。その性格は、所有権に基づく返還請求権にほかならない。
これに対し、 甲が回復されるまでの間は、 甲の所有権は、Cに帰属するという見解も主張されている。これは、占有者帰属説とよばれる見解である。この 見解によると、原所有者の回復請求権は、物の占有と所有権との双方の回復を求める特別な権利であると捉えられる。
(b) 使用利益の返還
次に、Aは、Cに対し、 不当利得を理由として、訴えの提起から甲の返還までの間の使用利益を返還するよう求めることができるか。 これが認められるときは、Aは、不当利得返還請求権と代価弁償義務にかかる権利とを対等額で相殺することができる。
一見すると、 占有者帰属説によれば、Aは、 使用利益の返還を求めることができないのに対し、 原所有者帰属説によれば、Aは、 使用利益の返還を求めることができることとなりそうである。 そうであるとすれば、判例は、原所有者帰属説にたっている((a)) から、この問題については、肯定説をとることとなるはずである。
もっとも、判例は、この問題については、否定説をとっている(最判平成12. 6.27民集54巻 5号1737頁)。 194条の規定が適用されるときは、原所有者は、① 代価を弁償して盗品を回復するか、それとも、②盗品の回復をあきらめるかを選択することができる。
他方、 占有者は、②においては、 盗品の所有者として占有取得後の使用利益を保持することができるにもかかわらず、 ①においては、代価弁償以前の使用利益を失うというのでは、占有者の地位が不安定になる。
これでは、同条の規定が原所有者の保護と占有者の保護とのバランスを図った趣旨と整合しない、というのがその理由である。
(参考)物権法[第3版] NBS (日評ベーシック・シリーズ) 日本評論社



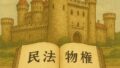
コメント